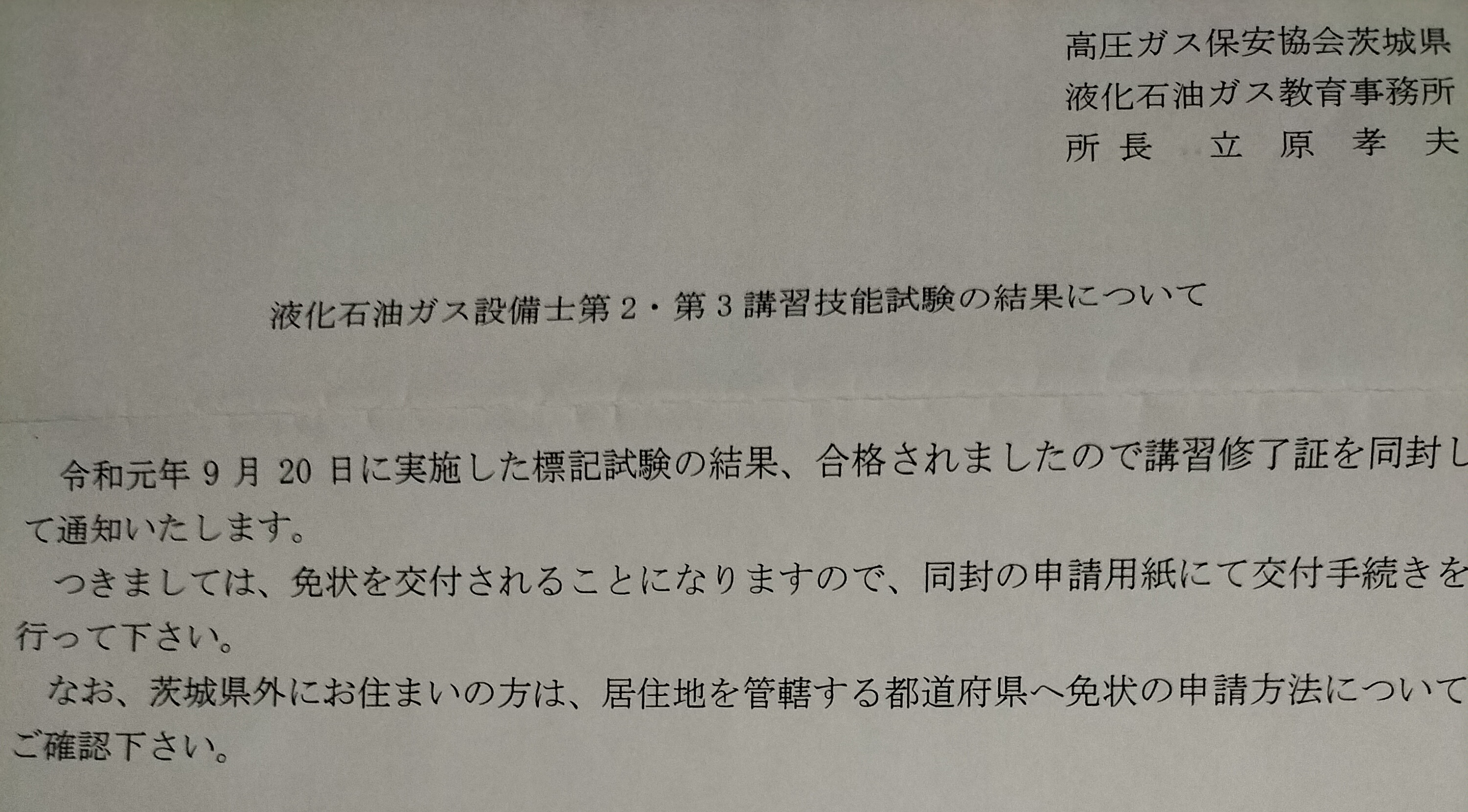短期離職を繰り返した30代の末路
30代半ばの佐藤健太(仮名)は、薄暗いワンルームマンションの部屋で、スマートフォンの画面をぼんやりと眺めていた。画面には、未読のメールと、応募した企業の「不採用通知」が並んでいる。かつては「次こそは」と前向きだった彼の心は、今、疲弊しきっていた。
健太の20代は、短期離職の繰り返しだった。新卒で入ったIT企業は、激務と上司の圧力に耐えきれず3ヶ月で退職。次の広告代理店では、華やかなイメージに惹かれたが、ノルマの厳しさと人間関係の複雑さに嫌気が差し、半年で辞めた。その後も、飲食、物流、営業と職を転々としたが、どれも1年未満で離職。理由は毎回「自分に合わない」「もっと良い環境があるはず」だった。
最初のうちは「若さ」を武器に、次の仕事がすぐに見つかった。しかし、30歳を過ぎると、状況は一変した。面接官の視線は冷たく、履歴書の「職歴の多さ」を指摘されるようになった。「なぜ短期間で辞めたのか?」「うちで長く働ける保証は?」という質問に、健太は曖昧な答えしか返せなかった。自信は徐々に失われ、応募する企業のレベルも下がっていった。
今、健太の生活は困窮していた。正社員の職は遠のき、派遣やアルバイトで食いつなぐ日々。貯金は底をつき、家賃の支払いにも追われる。友人たちは結婚し、家庭を築き、キャリアを積んでいる。一方で、健太は同窓会にも顔を出せず、SNSで流れる「成功」の投稿に目を背けるしかなかった。
心のどこかで「まだ挽回できる」と思いたいが、現実は厳しい。短期離職を繰り返した代償は、スキルや専門性の欠如だった。何か一つでも極めたものがあれば違ったかもしれないが、健太には「これができる」と胸を張れるものがなかった。転職市場での価値は低く、年齢だけが重くのしかかる。
夜、健太は考える。「あの時、辛くても我慢して続けてれば…」。だが、後悔だけでは何も変わらない。彼は一念発起し、プログラミングの勉強を始めることを決意した。オンラインの無料講座に登録し、ノートパソコンを開く。30代後半での再スタートは容易ではないが、諦めるにはまだ早いと自分に言い聞かせる。
健太の未来は不透明だ。努力が実るか、再び挫折するかはわからない。ただ一つ確かなのは、短期離職のツケは、時間と機会の喪失として、彼の人生に深く刻まれたということだ。